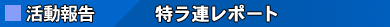ものごころついたときから映画館に通っていた。幼いころ母親につれられて行くのは決まって東映の時代劇だった。そのせいか母親は小学校しか行ってなかったのに、歴史に詳しかった。映画を通してだから歴史といっても、下世話ものに限られた。徳川5代将軍綱吉は“生類哀れみの令”により庶民が苦しめられていたのを、天下のご意見番水戸のご老公徳川光圀は戒めるために犬の毛皮を綱吉に送ったという逸話は映画の中の話であって、史実ではないと知っていたようだ。映画と歴史は別物という一線はあったように思われる。
東映の時代劇は勧善懲悪ものでストーリーはわかりやすかった。昭和20年後半から30年にかけて笛吹童子や紅孔雀、七つの誓いといったラジオドラマから映画化されたものを見た記憶がかすかにある。「七つの顔を持つ男しかしてその実態は多羅尾伴内」という台詞は子供の頃にはやっていて、遊びの中でもこの決め台詞を使っていた。
当時のスターは、中村錦之助、大川橋蔵をはじめ、片岡千恵蔵、市川右太衛門、大友柳太郎、月形龍之介など本ものの侍も負けるほど凛として本物の侍のようだった。
最近のことは忘れるのが早いが、子供の頃の記憶は残っている。小学生の頃はテレビは金持ちの家にしかなかったので、映画が娯楽の主役であった。幼い頃は東映の時代劇を親に連れられて行っていたが、中学生になると隠れて日活の無国籍アクション映画を見に行った。日活の映画は不良になるからというので学校では御法度だったが隠れて見に行くスリルを味わった。
 当時は至る所に名画座があった。昔、見そびれた映画や子供のころに見た映画を見ることができた。ただし“ぴあ”が創刊されるまでは、どこで何をやっているのかがわからなかったので、東京なら洋画は飯田橋の佳作座、邦画は銀座の並木座という、それぞれにテリトリーをもって通っていた。あるいは低予算作品のATG(アートシアターギルド)がかかっている日劇文化や新宿文化へ行っては訳が分からないなりに、これが実験的映画だとわかったようなふりをしていた。並木座では小津安二郎、黒沢明、木下恵介等といった往年の監督作品を見ることができた。その中で木下恵介監督の「日本の悲劇」は印象に残っている。昭和28年の製作だから世の中はまだ混とんとしていた。モノクロの画面は戦後の荒廃した風景が広がり、粗末な家に住み外で煮炊きをする庶民の暮らしが生き生きと描かれていた。主人公の望月優子は夫を空襲で亡くし、女手一つで娘と息子を大学へ進学させるまで育て上げる。ここまで育てるには闇屋の担ぎ屋を手始めに安酒場の女給、料亭の仲居と男に媚を売りながら稼いだ。そんな母親を毛嫌いして遠ざけようとする娘は妻子ある中年のもとに走り、息子は開業医の婿養子となる。養子先に息子を訪ねるが子供たちとの溝は深まるばかりで、消沈した母親は列車に飛び込み一生を終える。その列車には逃避行の娘と男が乗っている。という落ちがつく筋書きで、全体に暗い映画である。
当時は至る所に名画座があった。昔、見そびれた映画や子供のころに見た映画を見ることができた。ただし“ぴあ”が創刊されるまでは、どこで何をやっているのかがわからなかったので、東京なら洋画は飯田橋の佳作座、邦画は銀座の並木座という、それぞれにテリトリーをもって通っていた。あるいは低予算作品のATG(アートシアターギルド)がかかっている日劇文化や新宿文化へ行っては訳が分からないなりに、これが実験的映画だとわかったようなふりをしていた。並木座では小津安二郎、黒沢明、木下恵介等といった往年の監督作品を見ることができた。その中で木下恵介監督の「日本の悲劇」は印象に残っている。昭和28年の製作だから世の中はまだ混とんとしていた。モノクロの画面は戦後の荒廃した風景が広がり、粗末な家に住み外で煮炊きをする庶民の暮らしが生き生きと描かれていた。主人公の望月優子は夫を空襲で亡くし、女手一つで娘と息子を大学へ進学させるまで育て上げる。ここまで育てるには闇屋の担ぎ屋を手始めに安酒場の女給、料亭の仲居と男に媚を売りながら稼いだ。そんな母親を毛嫌いして遠ざけようとする娘は妻子ある中年のもとに走り、息子は開業医の婿養子となる。養子先に息子を訪ねるが子供たちとの溝は深まるばかりで、消沈した母親は列車に飛び込み一生を終える。その列車には逃避行の娘と男が乗っている。という落ちがつく筋書きで、全体に暗い映画である。
今の閉塞した時代と重なって見える。庶民の暮らしは劇的に近代化したが、心の中はあいも変わらず彷徨い、時代に流されているように思える。