| <index> | next>> |
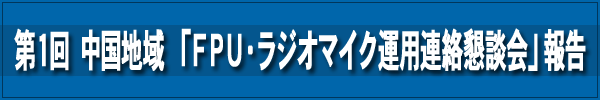
NHK広島放送局T-1スタジオと第1会議室
出席者数 35名(総務省、放送局、会員、特ラ連理事・事務局他)
広域圏以外の開催は四国そして東北に続いて、今回は総務省中国総合通信局(以下略して中国総通局)管内の懇談会を広島で初めて実施しました。
計画当初から実施終了まで、NHK広島放送局技術部 大塚 豊CE様が窓口になっていただきました。参加者は中国総通局から渡邊課長様の参加を得て、放送局関係23名、4会員から4名、特ラ連から理事長・専務理事・事務局職員と広島で1名の応援で合わせて4名そして「デジタルB型ラジオマイクの試聴・実証」を担当されたソニーの3名合わせて総計35名でした。

今回は、「デジタルB型ラジオマイク実機による試聴・実証」を会議に先立って行い、デジタルに馴染んで頂いた。
その後、通例になっている懇談会の意義と特ラ連の日常業務について、中国地域では初めてなので時間を割いた。最新の技術情報として、「特定ラジオマイク・デジタル化の経緯と今後」をソニーの松本様に講演していただいた。
意見交換として、「運用連絡のルールの確認」、中国総通局管内の放送局、会員からご協力頂いた「アンケート調査結果報告」そしてNHK広島局制技関口副部長様から、「ひろしま駅伝」の現状などのお話しをうかがった。
会を終えるに当たって、中国総通局の渡邊信男課長様よりご挨拶を受けて終了しました。
- 会員との事前打合せ
3会員から3名の参加得て、本会議前に理事長と専務理事で連盟の今後のあり方、地域実情など意見交換し懇談しました。
- 「デジタルB型ラジオマイク実機による試聴・実証」NHK広島放送局T-1スタジオ当連盟の小川一朗技術委員(ソニー)の参加を得て、ソニーの松本様より、デジタルラジオマイクのメリット、デメリットの説明を受け、その特徴について、実機を用いて、実証視聴をして頂き、現場からの質疑もあり、デジタルを身近に感じ取っていただいた。(詳細は112号に掲載予定です)
- 懇談会 NHK広島放送局第1会議室(以下、田中専務理事の司会進行)
田中専務理事の開会の辞があり、- (1)八幡理事長より挨拶
 広島の地は平成2年の創立期に、全国に当連盟の仕組みについて説明に伺った地でそれから20年たって感慨深いものがあります。
広島の地は平成2年の創立期に、全国に当連盟の仕組みについて説明に伺った地でそれから20年たって感慨深いものがあります。
これからも放送局の皆さんとは仲良くやっていきたいと思っています。
会員であれ、放送局であれ、心の通い合う仲間としてこれからも発展していきたい。との挨拶をいただいた。- (2)参加者の自己紹介
- (3)懇談会の意義(田中専務理事)
 配布資料により、特定ラジオマイク利用者連盟はいかなる業務対応をしているのか、放送局との関係を中心に特定ラジオマイク(A型)とFPUとが同じ周波数帯域を共用する為に必要不可欠の会であるとのご理解とご協力を求め、更に、チャンネルプランの基準、運用連絡の必要性など解説しました。
運用連絡の実情も配付資料により会員及び放送局からの連絡と調整依頼について実態に即した具体的な説明をするとことで、特ラ連の実業務対応の理解に努めました。
配布資料により、特定ラジオマイク利用者連盟はいかなる業務対応をしているのか、放送局との関係を中心に特定ラジオマイク(A型)とFPUとが同じ周波数帯域を共用する為に必要不可欠の会であるとのご理解とご協力を求め、更に、チャンネルプランの基準、運用連絡の必要性など解説しました。
運用連絡の実情も配付資料により会員及び放送局からの連絡と調整依頼について実態に即した具体的な説明をするとことで、特ラ連の実業務対応の理解に努めました。- (4)最新の技術情報 ( 松本純也 ソニーイーエムシーエス㈱))
 「特定ラジオマイク・デジタル化の経緯と今後」ついては、会議に先立って実施した「デジタルB型ラジオマイク実機による試聴・実証」の実演をベースにパワーポイントを用いて、メリット・デメリットなどを整理して話され、今後はこのデメリットの改善と特徴をうまく利用してデジタルの発展に寄与していきたいとの講演であった。(詳細は112号に掲載予定です)
「特定ラジオマイク・デジタル化の経緯と今後」ついては、会議に先立って実施した「デジタルB型ラジオマイク実機による試聴・実証」の実演をベースにパワーポイントを用いて、メリット・デメリットなどを整理して話され、今後はこのデメリットの改善と特徴をうまく利用してデジタルの発展に寄与していきたいとの講演であった。(詳細は112号に掲載予定です)- (5)特ラ連を取り巻く状況と意見交換
-
- FPU、A型ラジオマイクの運用連絡ルートについて(田中専務理事)
配付資料により、現在中国総通局管内でのFPUとラジオマイクの運用連絡ルート、中国総通局管外との関係について詳細説明をした。 - 各放送局と特ラ連の意見交換(田中専務理事)
- デジタルA型ラジオマイクに関するアンケート調査結果報告
調査用紙の設問は購入希望があるかないかそして購入価格の希望値の考えを組織としての考えと個人に分けた。解答は選択肢から選ぶ方法をとった。
回収は放送局10局、会員から6名のご協力を得ました。
購入希望は放送局2名はデジタルの特長(波数増、長距離運用、音質良等)会員1名は秘話性、先物買いであった。 購入希望なし放送局は組織も個人も製品を視聴検討したい、アナログで間に合っている、音断原因追及し難い、遅延であった。 会員はアナログで間に合っている、価格が高そうであった。 価格は放送局も会員もアナログよりも安くであった。 - 感想としては、デジタルのメリットは理解していただいていると思われるのでこのメリットを生かして、普及させていくことが必要ではないかと思った。
- デジタルA型ラジオマイクに関するアンケート調査結果報告
- FPU、A型ラジオマイクの運用連絡ルートについて(田中専務理事)
- (6)「ひろしま駅伝」の現況 (NHK技術部 制技 関口副部長)
 ひろしま駅伝の中継は地上受信基地を用いた伝送方式で、年々沿道筋の建物の変化、中継設備の設置を要請するが人間関係の変化などで苦労されている等、現場のご苦労話しを聞かせていただきました。
ひろしま駅伝の中継は地上受信基地を用いた伝送方式で、年々沿道筋の建物の変化、中継設備の設置を要請するが人間関係の変化などで苦労されている等、現場のご苦労話しを聞かせていただきました。- (7)来賓のご挨拶
- 総務省 中国総通局 無線通信部陸上課 渡邊信男課長様より、
 日頃、電波・放送行政にご協力頂きありがとう御座います。電波を共用するため放送局・特ラ連が一体となって、干渉・障害の未然防止に努力され周波数の有効利用を図っていることに敬意を表します。また、デジタルワイヤレスマイクの視聴・検証は、デジタルの特徴が分かり大変良かったと思います。
日頃、電波・放送行政にご協力頂きありがとう御座います。電波を共用するため放送局・特ラ連が一体となって、干渉・障害の未然防止に努力され周波数の有効利用を図っていることに敬意を表します。また、デジタルワイヤレスマイクの視聴・検証は、デジタルの特徴が分かり大変良かったと思います。
昨年、岩国市において企画されていた公演が米軍基地周波数と混信が生じるため中止になるという事例がありました。免許の条件に使用区域の制限がある場合もありますのでご注意頂くようお願い致します。情報共有等今後とも連携を深めて参りたいと存じます。とのご挨拶をいただきました。
当連盟として、周知不足に遺憾の意を表しました。
中国総通局管内の開催に当たり、お世話いただいたNHK広島放送局技術部岡田克也部長様のもとで、大塚 豊CE様には業務ご多忙の中各種対応をお願いし、快く御協力をいただきまして有難う御座いました。また、当日公務ご多忙の中を来賓として参加いただきました、総務省 中国総通局の渡邊信男課長様に御礼申し上げます。
| <index> | next>> |